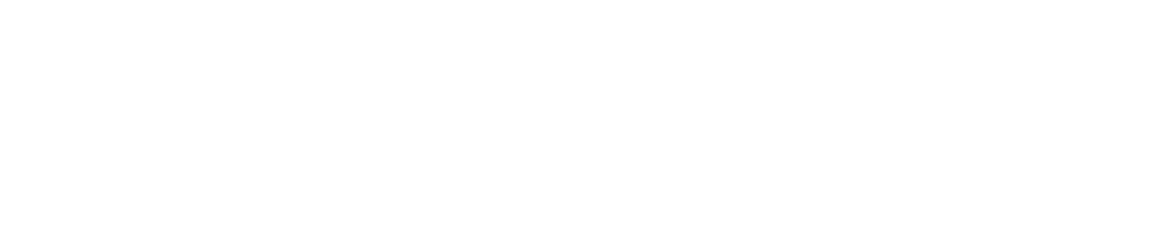
世論参加型ドラマ「フジテレビ問題」大丈夫か、日本。
2025年1月26日 配信

日本のテレビにとっては、トランプ大統領の政策転換や、欧州各国の右派政権の躍進や、イスラエルの暴走なんて、芸能人の性的なトラブルに比べたら小さな問題だったらしい。そうこうしている間に日本は世界からどんどん遅れをとり、既に負け組になっているのにそれを認めないどころか気づいてもいない。大丈夫か、日本。
そもそも、なぜ週刊誌は既に示談に応じた女性にインタビューを試みたのか。示談が成立したということは、当事者間でその問題は解決済みということだ。女性の方が実際、まだ何も癒えていなくて、苦しみの沼に溺れもがいていたとしても、その時点で示談という結論を選び取ったのだ。仮に、傷ついた女性が痛みに耐えきれずついそれを吐露してしまったとして、週刊誌は「示談になっている」という事実を知りながらその情報を流しても良いものなのだろうか?週刊誌側は隠された悪を暴き、世論の制裁を下すために一役買った正義の味方という風情でいる。この女性にインタビューを試みること自体、かなり非常識な行為だという批判がなぜ出ないのだろう。中居氏が「示談が成立し、仕事を続けられるようになった」と発表していたということは、当然守秘義務が盛り込まれているはずで、週刊誌がこれを発表することは、彼女にそれを違約させるということになる。逆に中居氏が受けた損害――引退せざるを得なくなったことで失われた収入、番組やCMへの違約金分――の請求をされるリスクを負わせる可能性もあるだろう。いや、当事者の女性は実際何も話していません、周辺からの聞き込みですということなら、事実は当事者しか知り得ないのだから、週刊誌の記事の信憑性はなくなってくる。
だから、週刊誌がどう言おうと、中居問題は既に「ない」のだ。当事者たちが解決したのだから。なのに、なぜそうもしつこく、突き回るのだろう。これは一種のハラスメントではないだろうか。メディハラとでも言おうか。
フジテレビのガバナンス問題の方が、社会的には大きな問題なのではないか。中居氏との会合の席をフジテレビの社員が設定したか否か、女性が相談してからの対応は適切だったのか。中居氏が出演していない番組からもスポンサーが降りていったのは、そちらの方の問題なのだ。「会見は失敗だった」と港社長は社員向け説明会で言った。この「失敗」という言葉は、彼の会見に対する姿勢、この案件に対するスタンスをよく表している。一企業のトップとして中居氏のトラブルに社員が関わっていないことと、被害者の人権を守るために誠実な対応をしたことを理解してもらい、問題を収束させるための会見であったのだから、むしろ反感を買ってしまい事態を更に深刻化させた点で、もちろん会見は失敗だった。
しかし、メディアとしての基本的な立場からしたら、いかに正確な情報を伝えられるかが重要で、クローズドの会見にしてしまったことは、成功か失敗かという以前に、明らかに「誤り」であり、あの会見自体が「不適切な行い」だった。
「あの会見は、メディアとして間違っていた。私はメディアとして許されない判断をしてしまった。」
というお詫びがまずあって然るべきだったと思う。今後、世間でどんな不祥事があったとしても、フジテレビのカメラは会見に入れなくても良いし、取材を受けなくても良いということになる。
つまり、フジテレビは、報道を否定し放棄したのだ。
フジテレビは第三者委員会に調査させることで事態の収拾を図るつもりである。ここでも注目すべきは、まずは調査の結果ではない。それ以前に、第三者委員会の選任の仕方が信頼回復できるか否かの岐路になるだろう。フジテレビをBPOで一度訴えた立場から言わせて貰えば、BPOに関わっている人物をこの第三者委員会に入れるのも絶対にやめていただきたい。
夫が都知事だった頃、フジテレビは朝6時に自宅に押しかけ登校のために出かける私の子供達にカメラを向けた。自分のことだったら我慢が出来た。が、子供の人権に関わることは許せなかった。証拠として求めているその子供達を写したビデオの提出をフジテレビ側は拒んだ。「以前ビデオを証拠として公開した時、それを苦に自殺者が出た。そのためビデオは放送以外の用途には使わないという内規がある。その内規に従って提出は出来ない。」ということだった。被害を訴えている側が提出を求めているのにも関わらず、証拠ビデオは提出しないでも良いとBPOは認め、証拠がないのでフジテレビ側が認めている6秒間のみについてしか俎上にあげられない、とした。ビデオを見れば、どんなに執拗にカメラが子供達を追ったか一目瞭然だったはずなのに。BPOは決して中立な組織ではない。メディア側の都合で裁判持ち込まれないよう作られた組織だ。どうか、ここに関係した弁護士らも第三者委員会には入れないでいただきたい。
そもそも報道とはなんぞや、というところが近年歪められてきていると思う。2009年にお亡くなりになった政治評論家の細川隆一郎氏がまだ活躍しておられた頃、メディアの新入社員たちとの座談会で「記者として大事なことはなんだと思う?」と問いかけた。何人かが「問題を捉える感性を身につけること」「視点のセンス」というようなことを答えた。彼はそれを一喝し、「全然違う。間違っている。記者に求められるのは、ただ、『事実を①ありのまま②正確に③迅速に伝える』それだけなのだ。君たちの感性だのセンスだのはむしろ介在させちゃいけない。それは受け手がそれぞれ判断することだ。」と言った。
けれど、今、結論ありきの報道のいかに多いことか。設定した結論に向けて操作してでも都合の良い情報のみを流す、或いは流さない。問題の重要さより、扇情的な内容を取り上げることで視聴率を稼ごうという、使い捨てニュースのいかに多いことか。そして、設定された結論に至るまではもうそのストーリーを修正変更しない段階に入る。第三者委員会がどういう報告をしても、どういう事実が出てきたとしても、設定されたそのストーリーに沿わなければよくてブーイング、エキサイトしていれば怒号と罵声が飛び交うだろう。単純な「勧善懲悪」のストーリーは最後まで変更して欲しくないのだ。かつて何度も同じことをしてきたのだから、その点はフジテレビもわかっていることだろう。もう、他のメディアと世論によって設定された結論に向けて、濁流に飲まれるように流されていくしかないのではないか。
理解に苦しむのは、総務省の対応だ。外国人比率が20%を越えていたという状況は同じなのに、なぜ東北新社の認可は取り消され、フジテレビは寛容にも取り消されなかったのか?なぜ東北新社からの接待を受け処分された官僚が、今はフジテレビの社外取締役におさまっているのか。総務省から来た社外取締役がいるのに、クローズドの会見は報道機関として問題があるという忠言はなかったのか。中居問題も、第三者委員会の結論もさておいて、
『会見を生放送させないテレビ局、報道の根幹を揺るがすテレビ局に、放送の認可はまだ必要なのか?』
という観点で、総務省はなんらかの反応を見せても良いのではないだろうか。
実は、この度出版することとなった「ピールオフ」には、テレビ業界での似たような飲み会のシーンが書かれている。女性たちを呼んで定例会を開くプロデューサーも出てくる。ここで誤解のないように断っておきたい。この小説は、この中居氏のトラブルが週刊誌に書かれるよりもずっと以前に書いたものだ。受賞自体が昨年の3月のことである。元ネタがないわけでもない。ますます物議を醸してしまうかもしれないが、フジテレビではなく他局での話から一部ヒントを得ている。事実は小説よりも奇なりというけれど、うーん、もっと頑張って書かないと、追いつけないなあ・・・・。
世論参加型ドラマ「フジテレビ問題」、最終回まで見守ろうと思う。
舛添雅美
コメント
0 件