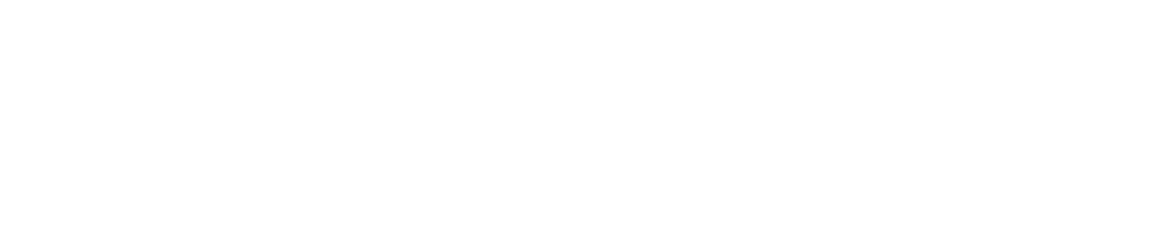
新しい世界
2025年4月18日 配信

満開の桜からハラハラと花びらが舞う。むせかえるような春の息吹。生物が発するエネルギーが大気の濃度を増しているかのよう。媚薬のような妖しい香りが仄かに漂い、鼻腔をくすぐり肺を満たし吐息まで春色に染める。と、それはやってくる。
それはホームページのお問い合わせフォームとか鳴り止まない電話とか郵便受けから忍び込む。今年も、ついにやってきたぁ!
曰く、「私の住む集合住宅の屋根に3本アンテナがあり、これを勝手に2本にまとめて電波を傍受している国家の陰謀を止めるよう、〇〇さんに言ってください。もう時間がありません。」はい?〇〇さん誰?あなた誰?締め切りいつ?
これはうちの事務所では季節の風物詩のようなものだ。「ああ、春だなあ。木の芽どきだなあ。」と思う。少々煩わしいという気持ちもあるが、それよりも見知らぬどなたかの突飛な発想力に感嘆する。他にも、「政治家となっている(私の夫の)甥っ子が実家にほとんど帰っていないことが、世界に大変な被害をもたらすので、すぐに実家に帰るように」との長い長いお手紙もいただいた。それは、お花と交信してわかったそうだ。夫に甥っ子がいないってことはわからなかったらしい。
長年、この木の芽どき通信を受けていると、ある種の傾向に気が付く。
「電波 、火星 、監視」 この3つは妄想の鉄板のようだ。何の接点もないであろう色々な方々がこれらのフレーズを同じように口にして、現実からかけ離れた話をする。彼らは、皆困っている。苦しんでいる。
おそらく誰もが経験してきている、新年度の未知の世界で揺蕩う想いや不安混じりの高揚感。それに加えてこの季節の自然からみなぎる生命力。焦燥感極まり、圧倒されて居た堪れなくなったのだろうか。彼らは救いを求めている。でも、そのパラレルワールドに、私は介入できない。する方法がわからない。ごめんなさい。何の助けにもならない。
ところが、我が弟はそれを難なくやってのける。
「火星からの電波の周期がこの時期になると変わるので、この歯が痛んで仕方がないのです。」
と訴える患者さんがいる。弟は、じっくりとその歯を観察し、以前撮ったレントゲンで既に神経を抜いた歯であることも確認し、患者本人にもう一度確認する。
「痛むのはこの歯だね?あなた、良く、うちに辿り着いたね。本当についているよ。この機材、まだ日本には2台しかなくて、うちも先月導入したばかりのものだけれど、火星からの電波を調整する電波をね、送り返すことができるんです。今、これで調整しておきます。ちょっと時間はかかるけど、2、3日で嘘みたいに痛みが消えるはずですよ。」
彼は落ち着いた笑顔で語りかけ機材を徐に調整し、患者に頷いてみせる。翌週、その患者が笑顔でやってくる。
「先生、ありがとうございました!本当に、嘘みたいに痛みが消えました。」
別の患者が痛みを訴えている。
「先生、私昨日、交差点を渡った時、電波で口の中が切れてしまって、歯茎からの出血が止まらなくなってしまって・・・」
「どれどれ、拝見しましょうか。」
患者さん自ら徐に総入れ歯を口から取り出して、自分でその入れ歯のピンクの樹脂をさしながら
「ほら、ここです。ここからの出血が止まらないんです。」
と涙目で訴える。
「ああ、これは痛かったでしょう?よく我慢しましたね。でもね、良い薬が開発されたんですよ。これ、まだ出来たばかりで、うちにも試供品でもらったのしかないんだけれど、これ、凄い効き目でね。患部に塗り込んでおきますから、これで様子みてください。あ、いいや、差し上げますよ。強力な薬だから塗りすぎないようにね。」
翌日患者が歓喜の報告に来る
「先生、ぴたりと出血が止まったんです。」
弟は、そういう治療法?を昔勤めていた総合病院の内科医の院長先生から学んだのだという。自分のその日の診察が終わったので、向かいにある内科を覗いていたところ、最後の高齢の患者さんが院長に秘密を打ち明けるように言ったのだ。
「先生、私、実はね・・・昨日の午後から脈が止まっちゃっているんですよ。どうしましょう。」
聞き耳を立てていた弟はそのままつんのめりそうになったのだけれども、内科の先生は落ち着き払って、
「どれどれ、うんうん、あ、いいね。今、脈は回復したよ。良かった!うんうん、普通に戻ったよ。ほら、ここ押してごらん。上出来だよ!」
「あ、ほんとだ。先生、私、生き返ったんですね。」
「うんうん、良かった。ここまで戻ったら、もう安心。あなたの心臓、上出来だよ!」
さて、ここで私が書きたいのは認知症になった父の話である。父は耳が遠くなった時、断固として補聴器を拒否し続けた。その結果、電話には出られなくなったし、テレビもほとんど聞き取れなくなった。情報源が限られるようになって認知症は一気に進んだ。
数年前のことである。それは、叔父からの一本の電話から始まった。叔父が電話をしてくるのは随分久しぶりのことだった。父から電話があったのだという。
「突然電話があってね。姉さんが寝たきりになって、もう起きては来られない状態になってしまったので、一応実家には伝えておかなければと思ってかけましたって言うんだよ。色々聞きたかったのだけれど、こちらからの話は全く聞き取れないみたいで、会話が成り立たなくってね。それで、どういう状況なのかまーちゃんに聞いてみようと思って。姉さん、相当悪いの?」
ゾワゾワと嫌な予感が腿のあたりから首筋まで一気に上がってきた。一昨日、行った時には、いつも通り元気で変わりなかったのに。おかしい。何かが起きている。
電話を切り、そのままバッグを掴み、家を飛び出し、猛ダッシュで特急に乗り込んだ。弟にLINEを入れると、
「パパは最近、ちょっとわからないことが多くなったから、いちいちそんなのに付き合っていたらキリがないよ。」
と冷静な返事が届いた。
「いや、絶対におかしい。私の妖怪アンテナがビンビンに反応しているんだもの。とにかくもう向かっているから。」
あー、いや、私、言っていることが木の芽どきな感じ?と急に我にかえる。この胸騒ぎ何?私、何に焦っているの?
「まあ、行って3人で美味しいものでも食べてくればいいよ。」
と弟は穏やかに言った。
実家の門を開けると、リビングの掃き出し窓ごしに、ソファにゆったりと座り庭の池を眺めている父が見えた。ごく普通の、日常の光景だった。玄関を合鍵で開けて入り、ソファにいる父に声をかける
「ああ、雅美か。」
「パパ、元気?叔父ちゃまに電話したんですって?ママは?具合でも悪いの?」
「ママ? ああ? 2階にいるんじゃないかな?見ておいで。」
弟の言う通りだったかもしれない。過剰反応だったかも。
「ママ〜?いる〜?」
返事がない。階段に何かシミがある。血だ、と気づく。点々と血のシミが続いている。壁にも血を擦ったあとが続く。大量の出血だ。目で血の行く先を追う。
その先に、母が血まみれで倒れていた。意識もなかった。
その瞬間の倒れている母の姿が脳裏に焼き付いたのはもちろんだけれど、むしろ、その後トラウマのように呼び起こされる記憶となったのは、あの時ソファに座り何事もないかのように庭を見つめていた父の姿だった。同じ家の中でもがき苦しんでいる妻をすっかり忘れ、ぼんやりと時間をやり過ごしていた父。恐ろしさに震えた。
母に関しては、なぜか私には、もう大丈夫だという安堵にも似た気持ちが湧いて、すぐにそれは確信に変わった。母は救急車が付く前に意識を取り戻し、水を飲んでしばらくすると、目を瞑り絨毯に横たわったまま、途切れ途切れに状況を話した。一昨日私が帰った後、階段から落ちたこと、なんとか2階まで這い上がって行き寝室にいた父に救急車を呼んで欲しいと頼んだのだが、父は電話がある階下に降りるまでにそれを忘れてしまい呼んでもらえなかったこと、自力で階下に降りて行こうとしたつもりが隣の部屋で倒れていたと。
父と母のその2日間を思うと、今でも目の奥に怒りとも涙ともつかぬ熱いものが込み上げてくる。何よりも許せないのは、母の搬送に付き添うため、父を一人家に残す直前に投げかけた私の言葉だ。
「パパ、どうして、ママがこんな状態なのに救急車を呼んでくれなかったの?せめて、私か弟に連絡してくれなかったの?電話の前に大きく番号も貼り紙してあるでしょう?」
父は悲しそうに
「動揺してしまって・・・。」
と答えた。私は、また父を傷つけた。まただ、また。父がこんな状態なのに、どうしてそんな言葉を投げつけているのだろう。
「そうよね、私も動揺してしまって・・・・。」
私はチラシの後ろに大きくサインペンで、
「ママと雅美は病院 夜には戻るから待っていて。」
と書いて父に渡し、「戻ってくるから絶対に家から出ないでね。家にいてね。」
と言い聞かせ救急車に乗った。
母は何ヶ所かを骨折していたし、腕の皮膚はずりむけ肉をあらわにしていた。
何ヶ月かそのまま入院することになり、私は2ヶ月間実家に通った。その間、父の世界では入院しているのは、父の母だった。
「母さんも、もうあの歳だから、もう退院は無理なのかもしれないなあ。」
と何度も呟く。私は、
「もうパパのお母さんは亡くなったのよ。入院しているのはあなたの奥さんでしょ?」
と残酷にも私の世界の事実を押し付ける。
「ええっ?母さんは亡くなったって?そうなのか?病院で亡くなってしまったのか?」
「随分昔に亡くなってしまったのよ。でも、孫も二人見られてとても幸せだったはずよ。今、入院しているのは、あなたの奥さん、私のママよ。」
「そうなのか、母さんはもういないんだな。でも、母さんは幸せだったんだな。孫も見られたしな。そうかな。そうだよな。」
父の中で長年連れ添った妻の存在は消えていた。弟と交代で、往復3時間かけて実家に通うことに疲れ果て、父は施設にお任せすることになった。
ある日、外出の後、施設に戻るために車の後部座席に二人で座っていると、父は私を見てにっこり微笑み、
「お姉さんは、どこの出身なのかい?」
と言った。私は実家のある地区を答えた。
「え?本当かい?私もだよ。どのあたり?何番地?」
私は実家の番地を答えた。
「ええっ!それじゃ、私の家のすぐ近くかも知れない。偶然だねえ!」
父は人懐こい笑顔を私に向けた。温かい良い人だ。
「ほんと、すぐ近くっていうか、同じ敷地かもしれない〜。」
と私が笑うと、父は私の顔をまじまじと見つめた。
「じゃあ、誰と同級生?どこの娘さんかね。」
「AさんとこのBちゃんが親友だよ。」
「おお、Aさんなら良く知っているよ。あそこの娘と一緒なのか。そうか、Aは隣に住んでいたことがあったものな。」
父は考えている。
「でもAにそんな年の娘がいるなんて知らなかったなあ。」
父の娘である私の存在はもう消えてしまっていたようだった。けれど、会うたびに、温かい信頼関係のようなものは築けたから構わなかった。ショックでもなかったし、悲しくもなかった。むしろ、私は頓珍漢なやり取りと楽しんでいたのかもしれない。
それに、父に溺愛された私の記憶は消えていないのだから構わなかった。
けれど、弟がある日、暗い声で電話をかけてきた。
「どした?」
「あのさ、今日、認知症関係の学会があったんだよね。それで、何かの参考になるかと思って聴いていたら隣の席の脳神経科医と仲良くなって話したんだ。そこで、ああ、と思うことを言われて、ちょっと僕一人ではしんどくなっちゃって。」
「はいはい、聞かせてください。」
「人ってさ、楽しいことよりも辛いことや苦しいことの方を憶えているって話。そりゃ、生存のために危険なことや痛い目にあったことの方を憶えておかなきゃっていうのは本能として当然だよね。それで、認知症になると、過去に戻ることがあるよね?その時、結局、一番強く記憶されているところに戻ることが多いわけでーーー。パパはさ、十四歳の時に父親が亡くなっているじゃん?母親も、結構早かったよね。」
弟は声を詰まらせた。私は、
「ああ!そういうことなのね・・・・」
と言って、弟は
「そういうことなんだよ。」
となんとか答えた。父譲りの穏やかさとユーモアのある弟も、父をそこから救えないのだ。父が妻を忘れても、娘を忘れてもよかった。でも、父が一番辛く苦しい時を再び生きていることは、私にも、弟にも、どうしようもなく悲しいことだった。認知症は、死を恐れずに済むよう神様が与えてくれたギフトのようなものだという話を聞いたことがあった。私は弟の話を聞くまでそれを鵜呑みにしていた。そう思いたかったからだろう。
父は、コロナの最中、亡くなる前、何度かふっとこちらの世界と繋がって、私と父の最後の会話は普通の父娘の会話であった。
舛添雅美
コメント
0 件